新年度のスタートに、新たに各学校に届く教材カタログの活用について、メリットと注意点をまとめてみました。 教材カタログは、情報の宝庫です。このページを参考に身近なカタログというアイテムを見つめ直していただければと思います。
教材カタログ活用のメリット
1.題材を行う際に、適切な材料用具を選択できる
カタログには、材料がセットされた教材キットだけではなく、材料単体での商品掲載もされています。例えば、教材キットに含まれている材料では、子どもが試しながら活動する余裕がない場合があります。そのような場合は、個人に教材キットを配るのに加え、クラス用、もしくはグループ用に追加で材料を用意しておくことで、活動に十分な材料を用意することができます。例えば、針金のキットに加えて単品の針金を追加で用意すると、試す活動で針金の特性を知ることができると同時に、キットだけのときより表現力豊かな作品が作れるのではないでしょうか。
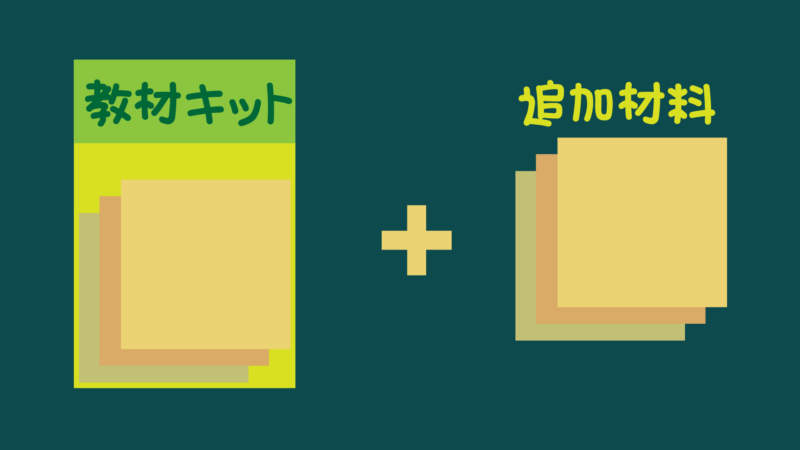
また、教材キットの中には、至れり尽くせりで、そのキットだけで授業ができるようにセットされたものがあります。しかし、場合によっては、これらには不要なものが含まれていることがあります。このような時にも、素材単体の規格や価格を知っておくことで、適切な材料用具が選択できるはずです。
2.題材で使える素材のバリエーションが広がる
掲載品目の多いカタログの場合、粘土ひとつをとってもたくさんの商品が紹介されています。黒い粘土とか、暗い所で光る蓄光粘土、そして水に溶けない紙粘土とかもあります。
たとえば、自分の宝物を粘土で作るような題材の場合、軽い粘土を使ってもいいですが、ここは宝物というイメージを重視して、どっしりとしたものの方がいいと思われる場合は、そのような粘土を見つけることができます。また、先ほどの水に溶けない粘土を使うと、題材自体の構成を変化させて、できた作品を水に浮かべて鑑賞するなんてこともできそうです。
3.新しい発見がある
ちょっとした空き時間にカタログをパラパラとめくるだけでも、新しい用具や技法に出会えます。例えば、スポンジローラーやスタンプにもこのようにたくさんの種類があります。これらを使うと、活動が楽しくなりそうです。作例もいろいろ掲載されているので、見ているだけでも楽しくなってきます。

一部の用具に関しては、使い方を詳しく解説してあるので、知らない方にとっては、これも新しい発見といえるかもしれません。
教材カタログの活用時の注意点
このように便利な教材カタログですが、活用には注意して欲しい点もあります。それは、商品をもとに題材を決定しないことです。それだと、作品を作ることが目的になって資質能力が伸ばせない可能性があります。題材を元に、題材を実施するのに必要な商品を決めてください。
もうひとつの注意点は、カタログに掲載されている作品例を意識し過ぎないことです。作品例の多くは大人の手によるものです。子どもが作ると作品例のようにはなりません。にもかかわらず、作品例のように作ろうとすると子どもに無理な活動をさせることになる恐れがあります。
いかがでしょうか。学校現場では、カタログがあるのが当たり前ですので、あまり感じられないかもしれませんが、題材に必要な素材の規格や価格を調べようとしても、ネット上で得られる情報はごくわずかです。Webカタログがあるのではと思われるかもしれませんが、現在のところ学校に提供されているような内容のものはほぼありません。材料用具の商品情報としては、今のところ紙の教材カタログが最も使い勝手がいいと言えるでしょう。
ですので、ぜひお手元の教材カタログをうまく活用して、教材研究や授業に活かして頂ければ嬉しいです。
このページの内容を動画で
このページの内容は動画でも解説しています。こちからご覧いただけます。
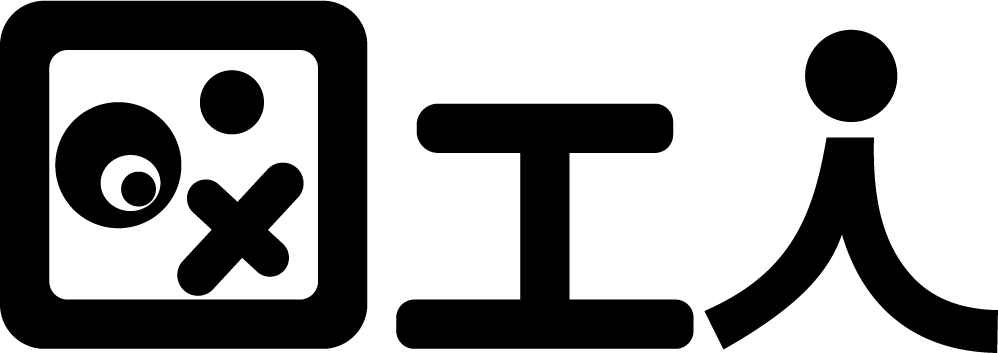
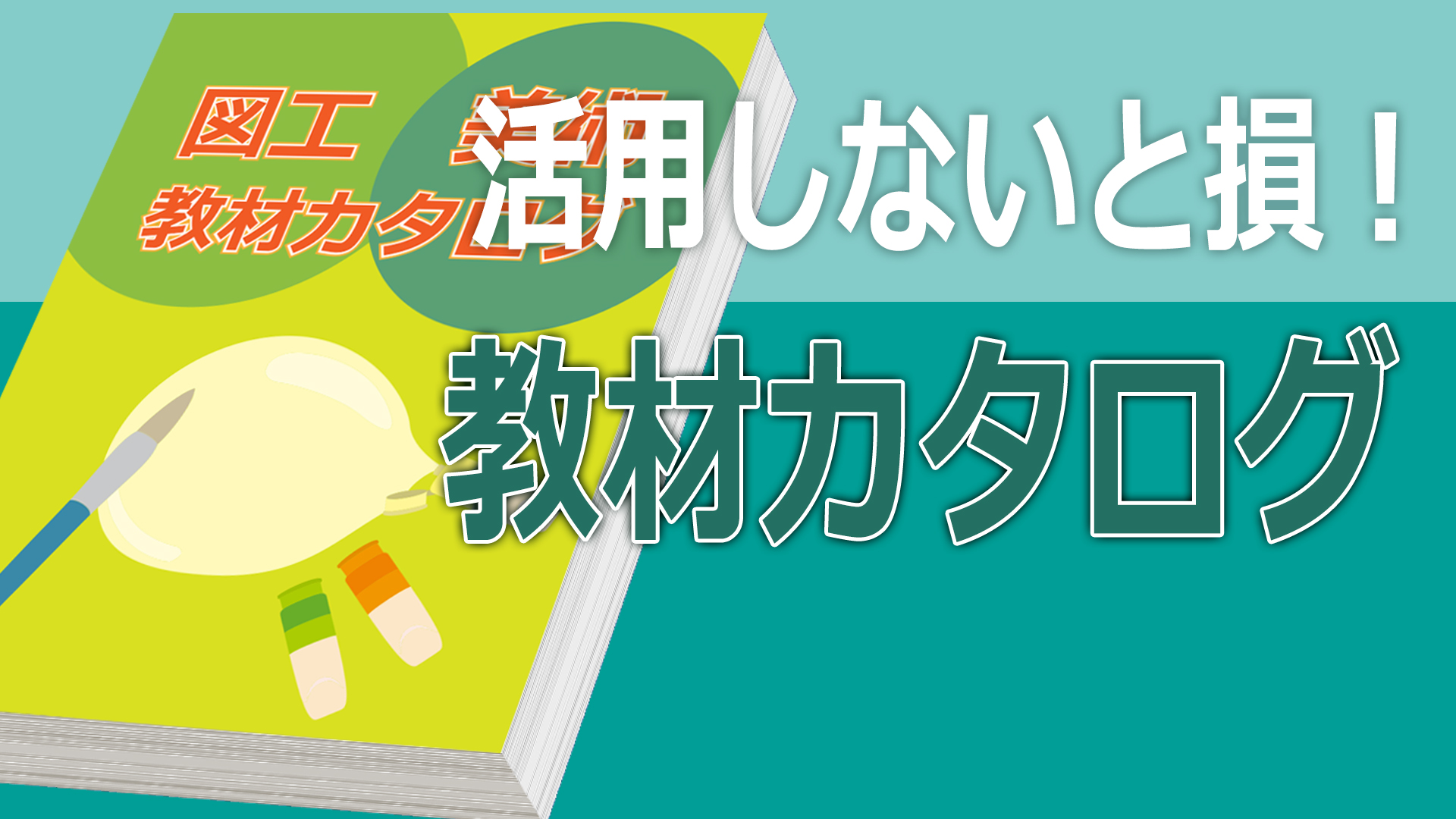
コメント