2月、3月は各教科のまとめの時期ですが、図工の授業においてもこれまでの学習を振り返る絶好の機会です。ただ、この時期は卒業・進級に向けた行事、さらには年度末の整理などが重なり、まとまった時間を確保することが難しくなります。また、指導計画的にも、図工に多くの時間が残されている訳でもないでしょう。そこで、特別に時間をかける訳ではないけれど、やってみるととても有意義な、学年末の時期だからこそ行ってほしいことについてまとめてみました。
子どもに任せる
結論から申し上げます。学年末の時期に行ってほしいことは、「子どもに任せる」ことです。それ用の題材を行ってもいいですし、以前から計画されていた題材でもいいですが、子ども自身が考え、工夫する機会をいつもより増やして題材を行いましょうという提案です。普段から子どもが工夫する活動が十分確保できている方には不要な提案だと思いますが、丁寧に指導されている先生ほど、子どもに任せる機会が減りがちだというのもあり得ることです。
そこで、学年末のこの時期に、先生の手を離れて、子どもが自身で考え活動する機会を図工のまとめとして行ってみるのもいいのではないでしょうか。

良い任せ方と良くない任せ方
子どもに任す図工にも、良い任せ方とそうでない任せ方があります。良い任せ方とは、これまで学んだ知識や技能、発想が活かせる任せ方です。貴重な学習の時間ですので、子どもが自身の考えで活動したとしても、そこに学びが必要です。
反対に、良くない任せ方は、子どもに丸投げするような任せ方です。例えば、「今日は自由に絵を描いてみましょう」というような場合、子どもの多くは漫然とした落書きやキャラクターの模写を行い始めるのではないでしょうか。用具について何も言わなければ、ほとんどの子どもは、マーカーや鉛筆などを使うでしょう。これまで、絵の具の技能にある程度の時間を費やして、子どもに身に付けさせてこられたとしても、これではそれらのまとめとしての学習にはなりません。
どのようなまとめの学習にするか
3年生で学習したえのぐの表現のまとめとして題材を設定するなら、用具を指定して、いろいろな色や形の描かれた、メッセージカードを作るような題材も面白そうです。題材名は「色、いろいろメッセージカード」とかはどうでしょう。子どもはこれまでの筆使いや混色などを思い出しながら、自分なりの表現の工夫ができるのではないでしょうか。他にもハサミで切ってカードの形を変えたり、リボンなどを別の紙で立体的に作る子も出てくるかもしれません。
これは用具の指定でしたが、テーマを指定して子どもに任せる方法もあります。例えば、6年生なら「卒業」というテーマを設けるのはどうでしょう。卒業という言葉からイメージを広げ、自分の描きたいものを自由に描く訳です。校舎を描く子もあれば、教室を描く子、友達を描く子、卒業式や卒業証書を描こうとする子もいるかもしれません。これまでの感情や心の状態を色や形に表す学習経験から、具体的な物や人ではなく、色やイメージで卒業を表現しようと考える子も出てくるでしょう。
このように子どもに任せるといっても、教師側がどのようなまとめの学習にしたいかを明確にしておいて、用具やテーマを指定するなどの手立てを行うことで、学びのあるまとめの時間にできると思います。その上で子どもができるだけ自由に表現できる機会を設ける、それがこの学年末の時期の図工にぴったりだと思うのですがいかがでしょうか。
このページの内容を動画で
このページの内容は動画でも解説しています。こちからご覧いただけます。
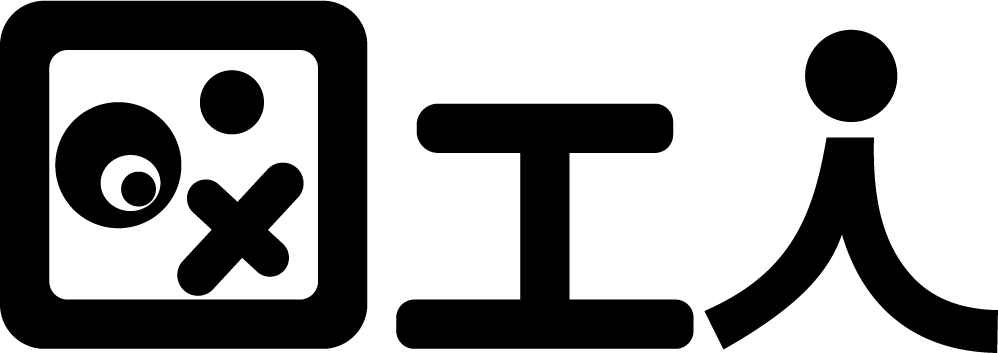
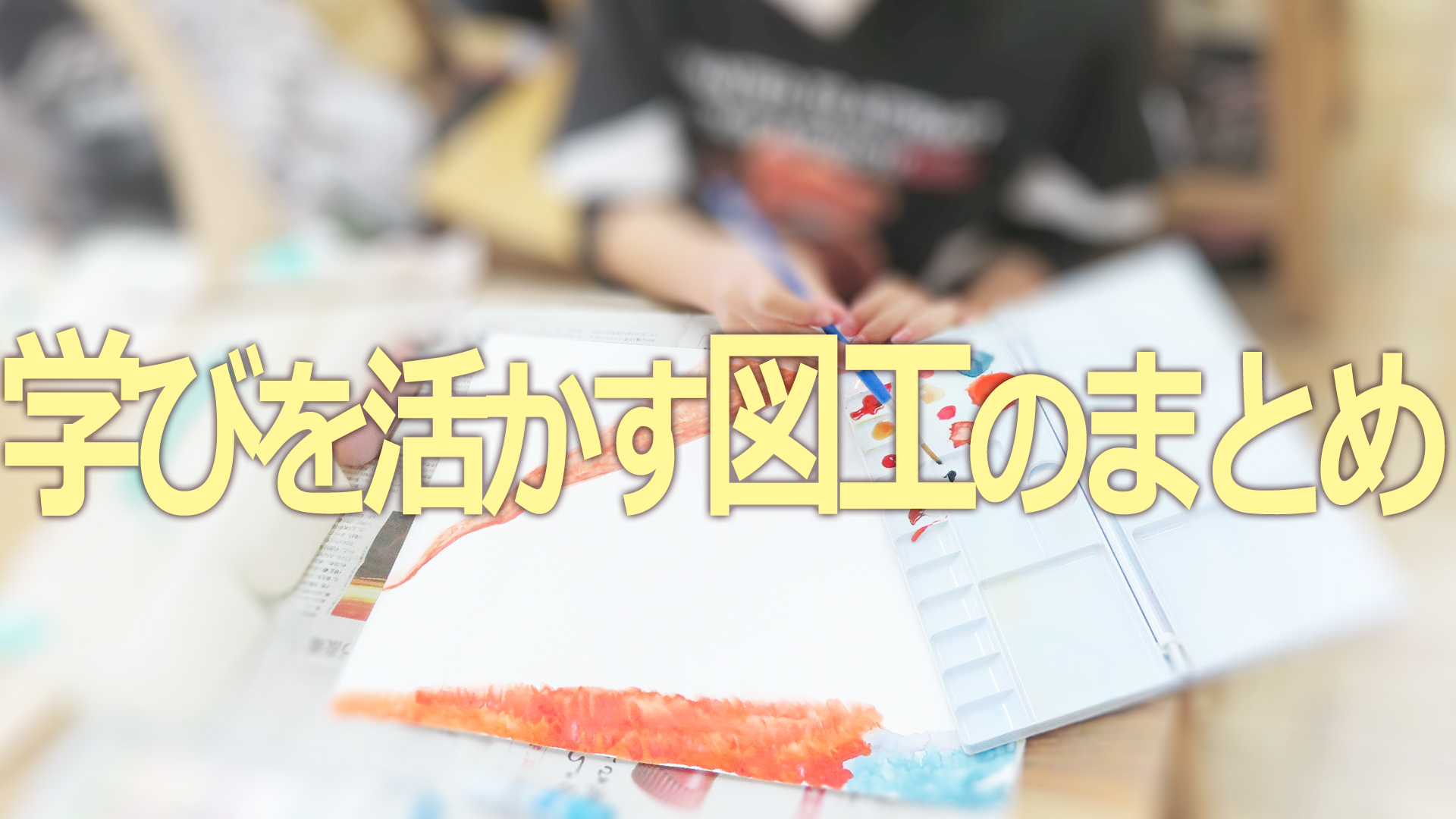

コメント